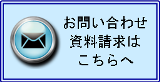| ネットスーパーの光と影 |
|
【ネットスーパー普及の背景】 ① 家庭でもストレス無くインターネットができるブロードバンド環境が整ったこと ② ECの経験が蓄積されてインターネットが実用的な購入チャネルの一つとして確立したこと ③ 女性の社会進出で買い物に行く時間の確保が難しい世帯が増えたこと ④ 高齢化で買い物の負担を減らしたいというニーズが高まったこと ⑤ 小売業の多様化でスーパーがコンビニエンスストアや低価格ショップに顧客を奪われていたこと ネットスーパー参入企業 ・イトーヨーカ堂、イオン、ダイエー、イズミヤ、紀ノ国屋 ・マルエツ、サンシ、サミット、オークワ、ユニー、他 ・ネット通販大手、住友商事 ※ 今後も地上デジタル化でネット通販人口の増加、核家族や高齢者の増加で宅配需要の拡大が予測され、ネットスーパーの利用者は右肩あがりの増加が見込まれる。 店でお客を待つだけでは売り上げは増えない。 【ネットスーパーの問題点】 ① 顧客の利便性=ネットスーパー側のコスト 価格はリアル店舗と同じで、安心の手渡しで当日時間指定までできる配送 →ピッキング・梱包・ドライアイス・配送などのコストに直結 ② 受注件数の壁 店舗の空きスペースを活用するため、その範囲内でしか受注を増やせない ※ 便利なサービスを無料で提供しているため、採算をとるのがきわめて難しいビジネスモデルである。 ネットスーパーはリアル店舗の補完であり、店舗に不可欠な御用聞きサービスだと位置づけて、店舗全体でコストを吸収してこそ成り立つという認識が必要。 → ピッキングは各売り場の担当者が行い、品質を確保する 梱包作業の専従者を最小限にし、コストを削減する 【ネットスーパー参入の目的】 ① 客数拡大 ② 顧客の囲い込み ※ 事業性追求というより、効果追求型ネットスーパーを目指す。 【ネットスーパーにおける今後の課題】 ① 高齢者の獲得 ・介護施設などにおけるグループ購入のしくみ ・地上デジタル化へむけてのシステム整備 ② 粗利ミックスのレベルアップ ネットスーパーの購入比率が高まれば、店全体の利益率は低下する。 →リアル店舗と同様に買い物の自由度を保ちながら、利益率を確保するための商品政策力が必要 ③ リアル店舗の競争力強化 スーパーがてがける宅配は、基本的に他社の顧客を奪えなければやる意味がない。 現在の売り上げ増加は週一回配送の生協、翌日配送の宅配からの顧客の流出もあるが、 今後は当日配送同士の戦いとなる。 →異業種を含め他社の顧客を奪える商品力、信頼度のアップが必要 ④ ネットでの注文の手間を軽減する ・レシピ掲載 ・材料のパッケージ化 ⑤ 配送コストの削減 ・ドミナント戦略 ・手渡しではなくロッカー保管による配送 ⑥ 広告やチラシなどを活用した知名度や利用率の向上 ⑦ データの活用 購入者、商品名、単価、日時、頻度など、POSより詳細なデータを活用 ・購入に至らなかったが購入を検討した商品の分析 ・配達時に口頭で商品に対する評価や意見の収集 → 新商品の開発案や既存商品の改善策 リアル店舗での品揃え 顧客毎のお勧め商品の紹介 などに利用 |